第21回 エネルギー・環境教育シンポジウム
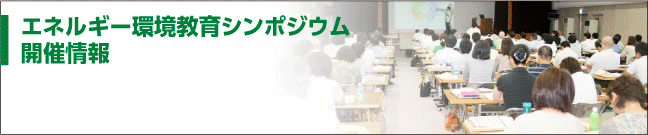
エデュコミュニケーション 21教育セミナー in 青森
~エネルギー・環境問題を考えよう!~
このたび、日本教育新聞社では文部科学省、青森県教育委員会、青森市教育委員会のご後援いただき、第21回を迎える「エネルギー・環境教育シンポジウム」を8月10日(金)青森市にて、開催しました。
さて、エネルギー・環境問題は、次代を担う児童・生徒に将来に関わる重要なテーマです。当シンポジウムは エネルギー・環境教育を授業ですぐに取り入れられる具体的なヒント を盛り込み、児童・生徒・教員がみんなで真剣に考えていただけるような内容となっています。
また、新たな試みとしまして、第1回「小学生・中学生によるエネルギー・環境問題アイデア・コンテスト」で優秀賞を受賞した児童・生徒らによる「プレゼンテーション大会」も同時開催しました。
開催情報
- 開催日時:
- 平成30年8月10日(金) 10:20~15:40
- 会場:
- 青森県観光物産館 アスパム 5F会議室
(〒030-0803青森県青森市安方一丁目1番40号) - 主催:
- 日本教育新聞社
- 共催:
- 八戸工業大学エネルギー環境教育協議会
- 後援:
- 文部科学省、青森県教育委員会、青森市教育委員会
- 参加対象者:
- 小学校・中学校・高等学校の教員、教育委員会関係者ならびに環境教育、エネルギー教育にご関心のある皆様(一般の方も可)など
- 協力:
- 日本原燃株式会社、青森県エネルギー教育ネットワーク会議
- 定員:
- 100名
- 参加費:
- 無料
多くのご来場ありがとうございました!

8月10日、青森県観光物産館アスパムで第21回「エネルギー・環境教育シンポジウム」(主催:日本教育新聞社、共催:八戸工業大学エネルギー環境教育協議会、後援:文部科学省、青森県教育委員会、青森市教育委員会、協力:日本原燃株式会社、青森県エネルギー教育ネットワーク会議)が開催された。小・中・高校などの教員や団体職員、児童・生徒、保護者など幅広い層が参加。約50名が最後まで熱心に受講した。
児童・生徒が輝けるステージに

平成最後の夏は災害に匹敵する豪雨と猛暑が相次ぎ、日本各地に甚大な被害が発生した。最初に登壇した藤田成隆氏(八戸工業大学名誉教授/前学長)は「子どもたちの将来に重要なテーマであるエネルギー・環境問題への理解促進のために、情報提供と交流を目的として回を重ねてきた。エネルギー・環境問題を子どもたちにどのように伝えていくか、そのヒントを持ち帰ってほしい」と挨拶した。
昨年好評だった小学生・中学生による「エネルギー・環境問題プレゼンテーション」を今年は一歩進めて、小学生・中学生による「エネルギー・環境問題アイデアコンテスト」の優秀賞を受賞した小学生3人・中学生3人の計6人が各部門の最優秀賞を目指して熱演。
藤田氏が審査員長を務め、ゲスト審査員に理科教育コンサルタントの小森栄治氏、青森県発明協会常務理事の藤本篤史氏を招いて、プログラム(別項参照)の最後に結果発表と表彰・講評を行った。
受講者から「レベルの高さを感じた」「メリット・デメリットを入れ、説明することでわかりやすかった」「挨拶もしっかりしていて好感を持った」「子どもたちの活躍の場が増えるので今後も続けてほしい」などの反響を呼んだ。
第21回 エネルギー・環境教育シンポジウムプログラム
開催情報
- 10:00 【受付開始】
- 10:20~ 【開会挨拶】
- 藤田成隆・八戸工業大学 名誉教授/前学長(シンポジウム・コーディネーター)
- 10:30~ 「科学マジックショー」
- 神田昌彦・平川市立竹館小学校校長
- 10:50~12:00 小学生・中学生による「エネルギー・環境問題プレゼンテーション」
- 弘前市立東小、六ヶ所村立千歳平小、青森市立横内中、青森市立古川中、八戸市少年少女発明クラブから、6 名の小・中学生が発表します。
- 【お昼休憩】
- 13:00~13:55 【基調講演・情報提供】
- 「スイスの地層処分場選定の科学の基礎を教科で学ぶ」
杉山憲一郎・北海道大学名誉教授、日本エネルギー環境教育学会顧問
- 13:55~14:10
- 八戸工業大学の学生による理科実験ブース
- 14:15~15:30 【実験講座】
- 「『理科は感動だ!』~主体的・対話的で深い学びを実現するエネルギー教育~」
小森栄治・理科教育コンサルタント
- 15:30~
- 小学生・中学生プレゼンテーション結果発表/表彰
- 15:40 【終了】
開催内容
基調講演・情報提供
「スイスの地層処分場選定の科学の基礎を教科で学ぶ」
杉山憲一郎・北海道大学 名誉教授/日本エネルギー環境教育学会 顧問

さまざまな教科から学べるテーマ
杉山氏の講演は「粘土」と「スイス」がキーワード。粘土は水や空気を通さない特徴があり、粘土質泥岩層に貝や魚が埋まっていくと、そのままの形で何億年も残り、化石になる。今夏の集中豪雨で河川が氾濫して粘土を含んだ泥に田畑が覆われ、雨水や空気が土に入っていかなくなり、農作物に多くの被害をもたらした。その反面、粘土質の泥が吸収した物質を外部に流失しない性質が役立つことも論じた。
福島県の原発事故で放出されたセシウムは、事故の翌年に収穫された玄米から基準値を超えたものはほとんど見当たらず、ここ数年は1kgあたり25ベクレルと出荷に問題のない数値だ。その理由は土壌に含まれる粘土鉱物がセシウムを捕らえて逃がさなかったため、と分析した。
「図画工作や美術の授業を通して児童・生徒は粘土の特性を学ぶ。縄文人は粘土で土器を作り、煮炊きして食物摂取革命を起こした。社会科の観点からも粘土の特性は学べる」と杉山氏は指摘する。
スイスではそうした粘土質泥岩層を対象に、国民投票を行い、放射性廃棄物の地層処分場候補地を選定しているという。地層が安定していれば人里離れた場所でなくてもよいと考えたスイス国民はフランスとの国境に近いジュラ山脈の地下に実験施設を開設し、研究を進めている。
「原子力と関係が深い青森県として、先生方や子どもたちが関心を持ち、自分なりの判断ができるよう教科を横断して学ぶことが重要だ」と結んだ。
実験講座
「理科は感動だ!」
~主体的・対話的で深い学びを実現するエネルギー教育~
小森栄治・理科教育コンサルタント

「電気の需要と供給体験ボード」を利用して
「エネルギー教育は正解がひとつではないことを学ぶのに最適」と提唱する小森氏が作成した体験ボードを使った実験講座。4人一組になって火力発電所が一基しかない離島の住民になり、不足しがちな電力事情を解消する方法を探求するシミュレーションゲームである。一台の手回し発電機を火力発電所に見立て、島全体の電力を、市民・工場長・市役所職員・電力会社社員という4者の立場から視点を変えながら「どう節電を進めるか?」「太陽光発電所を建設した場合、夜間や悪天候時の発電量の変動にどう対応するか?」など、多くの課題に取り組んでいく。
工場長からは「昼間の電力ピークを避け、夜間操業する」、市役所や電力会社の人々からは「節電をPRする。省エネ家電への買い換えを促進する」などのアイデアが次々と出てくる。その一方、考えを深めるにつれて「蓄電池を使えば、夜や曇りの日も太陽光発電を有効活用できるがコストがかかる。どうすれば普及できるか?」という新たな問題も発生する。
「企業努力で蓄電池の値段を下げる」「補助金を導入する」という受講者の声に小森氏は「普及前は高い蓄電池も大量生産すれば安くなる。補助金制度はみんなの税金を使うが、電気代を大きく節約できれば結果としては環境にもプラスになる。正解はひとつではないし、ときには対立する。授業でこうした模擬体験を子どもたちにたくさんしてほしい」と述べて拍手を浴びた。
小学生・中学生による
「エネルギー・環境問題プレゼンテーション」
「第1回 小学生・中学生によるエネルギー・環境問題アイデアコンテスト」の優秀賞に選ばれた小学生部門の3人、中学生部門の3人が会場でプレゼンテーションを行い、各部門の最優秀賞者を決定した。
小学生部門 最優秀賞
「新しい発電方法」
六ヶ所村立千歳平小学校 6年生 伊藤駿裕(いとうしゅんすけ)

環境保全と安定供給の両立
藤田成隆審査員長より「大変発想力に優れている」と評されたのは、二酸化炭素を排出しない発電方法2種。道路に発電用ローラーを埋め込み、自動車が通過することでそれを回転させて電力を得る。もうひとつは冬限定だが、積雪を地下に落とし込んで蓄積し、雪が溶ける際に放出されるエネルギーを動力として、タービンを回転させる方法。風力発電設備を見学したときに感じた、安定供給の方法は何か?という疑問から得たアイデアだ。
小学生部門 優秀賞
「食糧危機」
弘前市立東小学校 6年生 木村友香(きむらともか)
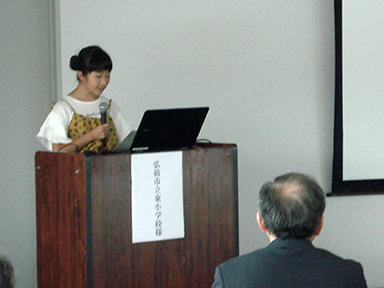
植物に優しい畑の開
植物にとって、成長するための安全な環境と豊富な水の提供が可能な場所として「海の上の畑」を考案。豊富な海水から生成した真水と、雨水を畑へ供給する。ドーム状の屋根はガラス製のため、日光を遮ることがなく、ソーラーパネルを設置することで、電力を得ることも可能になる。野生動物によって荒らされてしまうリスクも回避できる。ただし、収穫期には船を利用するため荒天に弱い、というデメリットも発案者から述べられた。
小学生部門 優秀賞
「日本の電気どうやって作ろう!」
六ヶ所村立千歳平小学校 6年生 橋本恵徳(はしもとけいとく)

より大きな動力を求めて
発電用のモーターを、より効率よく、大きな力で回すには、何を活用すればいいのか?
いつも動いている「何か」を探せばそのヒントが見付かるかもしれない……。そんな発想からスタートして、得られた答えは、飛行機の活用だった。時速にしておよそ1,000kmで飛行する機体に発電用のモーターを取り付け、世界中で運行させることができれば、大量の電気を得ることができる。そんな新しい発電方法が、未来には実用化されるかもしれない。
中学生部門 最優秀賞
「水と太陽光による無公害エネルギーを使った液体水素自動車」
八戸市少年少女発明クラブ(八戸市立長者中学校 3年生) 滝田直輝(たきたなおき)

ぜひ実現したい大きな課題
光触媒により水を酸素と水素に分解し、電気エネルギーを発生させ、車のモーターを回転させる。水素は酸化し、再び水に戻り、タンクへと溜められる。この循環によって走行する自動車は燃料が「水」で、さらに公害物質排出ゼロという「夢の車」だ。ただし、常温に近い温度で水素を液体化する方法と、その実現のための触媒の獲得という大きな課題は未解決だが、「各プロセスの明確な解説が大変によかった」と高い評価を得た。
中学生部門 優秀賞
「新しい発電方法」
青森市立古川中学校 3年生 天野流空(あまのりく)

電力の自給自足を実現
現在、民間企業の施設で実用化されつつある「発電床」。基本的な構造は、2種類の金属で電圧素子を挟み、それに圧力を加えて電力に変換する。これを道路や建物などの施設に埋め込めば、人間や車両の往来で得られる圧力によって、施設自体で電力の自給自足が実現できる。現在、ライターやゲーム機などに活用されているこの機能は、今後の技術の開発によって、日本のエネルギー自給率を高めることに貢献できると期待が集まった。
中学生部門 優秀賞
「海のゴミ収集車」
青森市立横内中学校 2年生 下斗米博士(しもとまいひろせ)

生物が快適に暮らせる地球へ
海岸に漂着するゴミは、日本の場合、年間約19万トン。これは東京ドームのおよそ半分の体積にあたる。処理に莫大な費用がかかるだけでなく、地球環境へも多大な影響を及ぼしている現状を抑制するために、海洋を自在に動き回ることができるゴミ収集マシンを開発するのはどうだろう?
動力となる電力は、太陽光と波力を活用。海面と海底のゴミを吸引し、一定量を回収したら、陸地のしかるべき集積地へ移動する、という提案である。
科学マジックショー
「科学マジックのすゝめ」
神田昌彦・平川市立竹館小学校長

独特の衣装で登場した神田氏は愉快なサイエンスショーや科学工作を通じて理科の楽しさを伝えている。参加者からも「空気が和む。非常に良いショーだ」と大好評だった。
八戸工業大学の学生による理科実験ブース
身近な雑貨や無料アプリで教材作り

会場の一角にあるブースでは100円ショップの雑貨を利用した教材や実験装置、無料アプリなどを使った教材を紹介。電子レンジで白熱電球を灯すと場内から歓声が上がった。
結果発表・表彰
小学生・中学生による
「エネルギー・環境問題プレゼンテーション」

【小学生部門】 最優秀賞
■六ヶ所村立千歳平小学校6年生 伊藤駿裕さん
「新しい発電方法」

【中学生部門】 最優秀賞
■八戸市少年少女発明クラブ(八戸市立長者中学校3年生) 滝田直輝さん
「水と太陽光による無公害エネルギーを使った液体水素自動車」
